みなさんこんにちは!
今回コミュニティ演習第5回のブログを担当させていただきます。
5月19日の授業では、授業前半は武蔵野市役所の高齢支援課の方々にテンミリオンハウスについて貴重なお話を伺い、質問をさせていただきました。授業の後半は教室でコミュニティ演習の集大成としての学内の発表とパンフレットづくりについて意見を出し合いました。
職員の方々のお話は成蹊図書館のプラネットと呼ばれる一面ガラス張りの近未来なドームで聞きました。ほとんどの学生がプラネットを初めて利用したので、ガラス越しの見晴らしに感動していました!
まず武蔵野市にとってテンミリオンハウスがどのような位置づけなのか、できた背景とともにご説明していただきました。介護保険制度ができる少し前から市の福祉施策に関する話し合いが始まっていたそうです。もともと武蔵野市は高齢者の福祉に対して手厚いサービスをしてきたのですが、介護保険の導入によってそれまでのサービスを受けていた人の中でサービスを受けることができない人が出てきたそうです。その方たちがいける場所としてのテンミリオンハウスが作られました。このように支援を継続する姿勢は全国的にみても革新的な自治体であると感じました。お話の中で紹介されていた『武蔵野市100年史』にもテンミリオンハウスの記述があるそうです。皆さんもお時間あるときにぜひ目を通してみてください!(武蔵野市のホームページからアクセスできます。)
このようにテンミリオンハウスは武蔵野市を代表する福祉事業の一つで、25年以上前から今まで様々な協議と調査を重ねて運営してきたそうです。また、地域の共助のために市役所ができる役割は場所と財源の支援だとおっしゃっていて、自分たちの手で地域を良くしようという武蔵野市の方々の意識に合った支援だと思いました。
一方で、25年間で生まれてきた課題についても教えていただきました。物価や人件費の高騰、利用者の固定化、新たな担い手不足を主な課題点として挙げられていました。どれもすぐに解決することが難しいため、私たち学生でもできることがないか考えさせられました。
この後ひとり一つずつ職員の方に質問させていただきました。人手不足の原因や予算に関する質問、男性の利用者さんを増やすための工夫などについてさらに詳しく伺うことができました。
次に授業の後半では教室に移動し、7/8のコミュニティ演習成果発表会の具体的な発表内容とパンフレットの構成についてそれぞれの班で意見を出し合いました。1時間近くある発表の中で、テンミリオンハウスができた経緯と各テンミリオンハウスの魅力をどのように伝えるかたくさんの工夫が出てきました!また、テンミリオンハウスだけでなく、ムーバスや武蔵野プレイスといったほかの武蔵野市の取り組みが身近にあることも伝えたいというアイデアもでました。ちなみに発表会とは別に作成するパンフレットの基本的なデザインは私たちがしていくことになりました。お楽しみに!
さらにまとめとして私たちから見たテンミリオンハウスの課題に対する解決策の提案についても考えました。今回高齢支援課の方々から聞いた現状の問題点を中心に私たち大学生がどのように関われるか、インターネットをうまく活用できないかなど意見がたくさん出ました!今後もいくつかテンミリオンハウスを見学させていただく予定なので、そこで新たに見つけた問題点や改善点も付け加えていきたいです。
今回のブログはここまでとさせていただきます。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
第6回の授業では「川路さんち」というテンミリオンハウスに見学に行ってきます。次回のブログもお楽しみに!
文責:暴れん坊症候群
_250604_7.jpg)
_250604_43.jpg)
_250604_28.jpg)


_250604_10.jpg)
_250604_1.jpg)



















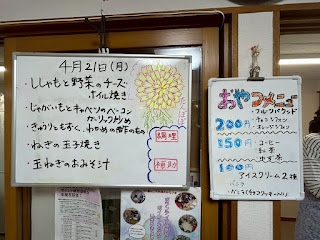



.jpg)
.jpg)